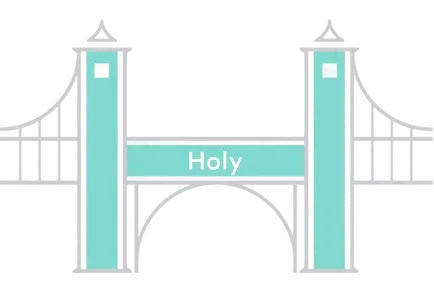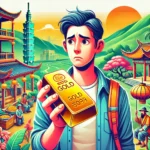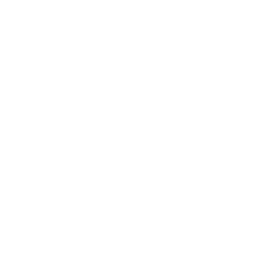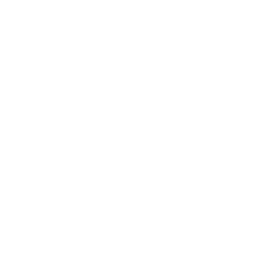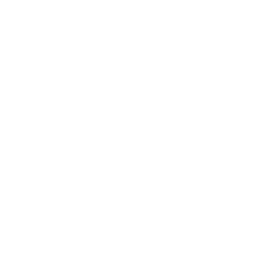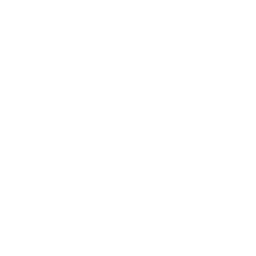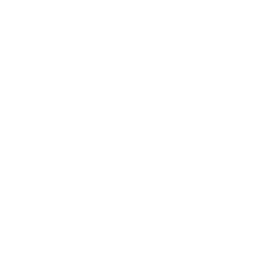昔と今の金税制の違いと節税法
税制は時代と共に変化し、その影響は私たちの生活やお金の管理方法に大きく関わってきます。本記事では、昔と今の金税制の違いと節税法について詳しく解説します。まず、歴史的な背景を振り返ることで、昔の税制がどのように形成され、どのような特徴を持っていたのかを理解します。次に、現代の税制の仕組みや、課税の公平性の重要性について考察し、どのように現在の制度が私たちに影響を及ぼしているかを探求します。
続いて、節税の基本に触れ、その目的や効果的な方法を紹介します。特に、昔と今の節税法の違いに注目し、歴史的な認識と現代における戦略を比較することで、今の時代に適した実践的な節税テクニックを学ぶことができます。この記事を通じて、税制の変遷を知り、実生活に役立つ節税の知識を身につけることで、あなたのお金の管理の見直しに繋がることでしょう。
昔の金を用いた相続性の節税の概要

相続税は、すべての財産が課税の対象になる税金ですが、日常礼拝に使用されている祭具については非課税とされています。昔の金を用いた節税は、仏壇にある「ちーん」と音を鳴らす「おりん」と呼ばれる仏具を金で作り、非課税にして相続税対策をするというものです。
現代でも金仏具スキームは使えるのか
日常礼拝に使用されている祭具については非課税ですが、「ただし、骨董価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかる」と法律上規定されています。
「金の仏具スキーム」が流行したため、相続税が非課税となる仏具などは、あくまで日常的に礼拝用として使用することが社会通念上認められる程度の物でなければならないというのが厳格になり、その家の暮らしぶりに見合わないほど高額なものだったり、商品性が高く転売目的などと認定されるような場合は相続税の対象となっていきました。
現在ではもう使えないのか
現在でも、仏具店や金取引所では純金製の仏具が取り揃えられています。実際には、非課税となる場合もあれば、課税される場合もあります。そのため、各家庭の状況に応じて、適切な範囲で祭祀財産を購入することが望ましいでしょう。
相続税対策のやり方は他にはないのか

贈与税の基礎控除の年110万円を利用したものです。
毎年、110万円以内の地金を渡していくという方法で、理論的には非課税で財産を渡すことができます。
ただ、こちらも流行したため、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、課税されるようになりました。
節税対策のまとめ
結局どの方法も非課税となる場合もあり、課税される場合があります。
ただ、贈与していないのにしたことにする等、不正を行えば必ず課税されます。
現代における節税法は、昔のように合法的な抜け道を探すといった考え方から、より戦略的かつフレームワークに基づいた計画的なアプローチが主流となっています。特に、税制はより厳格化され、透明性が求められるため、誤解を招くような手法は避け、長期的な戦略が重要視されています。
以上のように、節税法のいずれにおいても計画的なアプローチが重要です。今後の税制改正に対応しつつ、適切な節税戦略を構築する必要があります。